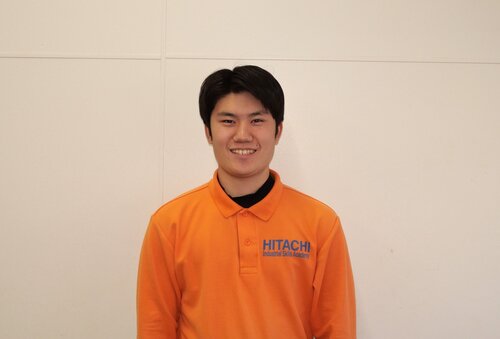東京都溶協、高校生・教員対象に溶接研修 2日間で延べ46人が参加
(「溶接ニュース」2025年9月23日付 18面より)
東京都溶接協会(都溶協、横田文雄会長)は8月4日と7日の2日間、都内の工学・工業系高校の生徒と教員向けに溶接実技研修会を開催した。4日は城東職業能力開発センター(足立区)、7日は多摩職業能力開発センター(昭島市)を会場とし、両会場合わせて高校7校から延べ46人(生徒33人・教員13人)が参加。同研修会初参加者は被覆アーク溶接、経験者は半自動溶接に挑戦し、実習を通じて基礎的な技能の習得に励んだ。
(参加者一同)
同研修会は高校生に「溶接に触れて興味を持ってもらう」ことと、教員の実技指導力向上を目的に毎年実施されており、会員企業の溶接実務者が講師となって生徒、教員の指導に当たる。研修会への参加をきっかけに溶接の面白さに目覚め、都溶協主催の若手人材育成溶接コンクール(高校生溶接コンクール)に出場した生徒も多く、都溶協にとって活動目的のひとつである「溶接技能の普及」に資する重要な定例行事となっている。
研修会に参加した生徒と教員は技能の習得度に応じてグループ分けがなされ、それぞれ異なる研修テーマに臨んだ。研修会初参加者を含む溶接初心者は被覆アーク溶接の指導を受け、過去の研修会参加者を含む溶接経験者のうち生徒は半自動溶接にチャレンジし、教員は被覆アーク溶接の基礎を再確認した。
初心者グループははじめに安全教育ビデオを視聴した後、講師から保護具の着用や溶接機の始業前点検などの基本を教わった上で被覆アーク溶接の実習に移った。講師が手本を見せて溶接棒と母材との距離、運棒時の角度と速度など細かいポイントを一つひとつ丁寧に説明するとともに、アーク出しやビードオンプレートのコツを的確にアドバイスすることで溶接がほぼ初めてという生徒も瞬く間に上達していた。
経験者グループの生徒は半自動溶接に臨み、ビードオンプレートで被覆アーク溶接との違いを意識しながら半自動溶接機を使用した際のトーチ操作に慣れていった。その後、V型開先の試験体を用いて多層盛りの練習を重ね、ビードをきれいに仕上げる方法について講師のアドバイスを基に繰り返し実践。最後は中板(板厚9ミリ)の下向突合せ溶接(A2F)にも挑戦した。
(真剣に実技に取り組む生徒に講師の指導も熱が入る)
会場の一画ではリンカーンエレクトリック社製のバーチャル溶接トレーニングマシン(VRTEX360コンパクト、鈴木機工提供)を置き、被覆アーク溶接のビードオンプレートを体験できるシミュレーション・コーナーを設営。練習の合間に生徒や教員らが仮想空間内での溶接訓練の感触を確かめる姿が見受けられた。
生徒、講師に研修会参加の感想を聞いた。
今回が初参加となる八王子桑志高校3年生の宮崎悠輔さんは「授業でも実際に溶接を行ったことはなく、初めての経験となる。火花がバチバチに飛ぶので危険はあるが、やってみると面白く夢中になった。将来の進路はまだ検討中で、就職先の選択肢を増やすため、まずは溶接を経験してみたかった」と話す。
東京科学大学付属科学技術高校2年生の露口新さんは「4~5回目の参加で、半自動溶接は今回が初めて。思っていた以上にトーチが重かったが、慣れてくれば手棒よりも扱いやすいかもしれない。きれいなビードを引けたときの達成感が溶接の醍醐味であり面白さだと思う。将来は自動車開発の仕事に就きたいと考えており、ものづくりに必須な溶接の技術をもっと知りたい」という。
今回の研修会講師との中には、第65回東京都溶接技術競技会の優勝者で今年の全国競技会富山大会に出場する日鉄溶接工業の粕谷稜人氏が名を連ねており、「ほかにも指導員の経験があり、人に教えることで自分の勉強になることは多い。高校生は教えたことを素直に聞いて実践しようとするので呑み込みが良く、教え甲斐がある。今後もこうした機会があればお手伝いしたい」と語った。
(「溶接ニュース」2025年9月23日付 18面より)




 SNSシェア
SNSシェア