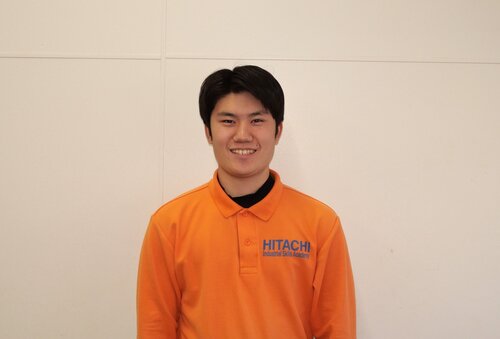優勝者インタビュー 全国選抜高校生溶接技術競技大会in新居浜 半自動最優秀賞 橋本侑磨選手(今治工校)
(「溶接ニュース」2025年9月9日付 2面より)
去る8月1日、9回目となる2025年度「全国選抜高校生溶接技術競技大会in新居浜」が日本溶接協会四国地区溶接技術検定委員会実技試験場(愛媛県新居浜市)で実施された。17道県36人が溶接技術を競った今回の大会で、炭酸ガスアーク溶接部門(半自動)を制した橋本侑磨選手(愛媛県立今治工業高校)に話を聞いた。
(橋本選手)
私が溶接を始めた理由は、1年生のときに溶接の授業があり、他の技術・技能と比べても「技能者の腕」が求められるように感じ興味を持ったからだ。興味を持ったものの、今治工業では1年生は10時間、2年生は20時間、3年生は30時間しか溶接の授業時間がないため、より専門的に学ぶことができると聞いた「機械造船部」に入部した。
溶接のこだわりとしては「電流・電圧を調整する」こと。これは溶接棒を持つ手を動かす工法の一つであるウィービングを初期に褒められたことがうれしくて、練習してきたため、溶接姿勢が2年生になる頃には定まっていたからだ。姿勢を崩さず、電流値といった設備の出力を調整することで作品精度を上げる方法を選んだ。
ありがたいことに、当校には同じ大会の前回優勝者である武田佳也さんが手掛けた溶接作品が豊富に残っている。一定量、私が溶接ビードを上手に引けるようになった後も、前年度の「日本一」の溶接ビードと並べてみれば、まだまだ精度が荒い点が見つかった。
日本一になってからというもの「どうすれば溶接が上達するのか」と質問されることが増えた。溶接に限ら
ずに、上達には練習以外の方法はないのだが、「上達してきた後でも、さらに課題を見つけて克服する」ことの大切さを、機械造船部の一色卓也先生から口酸っぱく教えられてきた。
例えば9ミリ鋼板を溶接する場合、私の場合3層肉盛して仕上げており「3層目が寸分狂わずに同じ高さで揃っているのか」といった部分を武田先輩の溶接ビードと比較。同じように「幅が1ミリ違わずそろっているのか」といったポイントも、気が付くことさえできれば、修正することもできる。
凄腕の先輩が同じ高校にいたこと、その先輩が手掛けた作品と自身の作品が「どのように違っているのか」を言語化してくださる一色先生の存在こそ、私の溶接技能が成長できた屋台骨だ。
(橋本選手の作品(左)と昨年度の最優秀作品)
将来の夢は造船事業所で溶接士として働くことだ。私が暮らす今治市には、日本最大の造船事業所である
今治造船をはじめ、日本有数の造船事業所が立ち並んでいる。日常的に造船の風景を眺めてきたこともあり、それ以外の選択肢は考えていない。できれば日本最大の今治造船で溶接の腕を振るいたい。溶接は見ているだけでは魅力が伝わりにくい技能だが、実際に触れれば楽しさが分かる奥行きのある技能だ。
(「溶接ニュース」2025年9月9日付 2面より)




 SNSシェア
SNSシェア