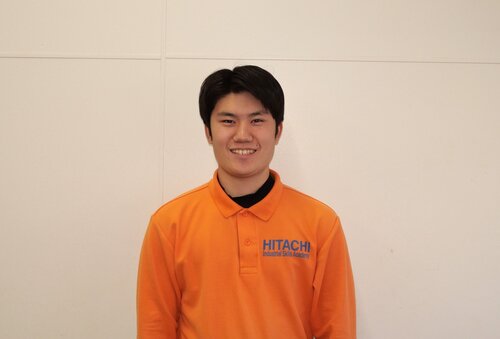溶接の面白さと奥深さが 進路選択の決め手に(高校生溶接士の将来像)
(「溶接ニュース」2025年6月10日付 1面より)
高校在学時に溶接の面白さと奥深さに触れ、高校生対象の溶接コンクールで入賞するほど夢中になって練習に励み、進路の選択でも溶接士となる道を選んだ瀧下桜介氏。溶接技能の向上に努めながら自身の知見や経験をさらに高め、一流職人に匹敵する溶接ロボット開発を夢見る同氏に話を聞いた。
瀧下氏は都立科学技術高校に入学し、部活動の中で溶接の面白さに目覚めた。当時の顧問が同校に溶接を根付かせようと熱心で、東京都溶接協会の高校生溶接研修に参加して溶接の技量が上達する喜びを知ることになり、以来「(溶接に)ハマった」という。
高校2年生で同協会主催の第9回若手人材育成溶接コンクール(2022年12月-23年1月開催)に初挑戦。そこで出場権を勝ち取り、満を持して臨んだ第13回関東甲信越高校生溶接コンクール(23年4月開催)では見事に優良賞を受賞する健闘ぶりを見せた。
(瀧下桜介氏(前川製作所))
このような優れた溶接技能に加え、形状記憶合金の応用に関する研究レポートで「電気学会高校生みらい創造コンテスト」の佳作を受賞するなどエンジニア気質の持ち主でもある。エンジニアらしい、問題の原因を分析して結果を導き出す論理的思考力が溶接技能の向上に一役買っている面もあるようだ。
そんな同氏も本格的に溶接の練習を始めた頃は苦戦の連続でその難しさを痛感した。「溶接は思っていたほど簡単ではなく、細かいところまで気を配らないと上手にビードが引けず、試行錯誤しながらより良い条件を見つけ出していくのは大変な作業だと分かった。その分だけ徐々に上達していく手応えに探求心が刺激され、自分なりの条件を組み合わせて望む結果を出せたときの痛快さは例えようもなく、そこに溶接の魅力を感じる」と語る。
進路を決める上ではものづくりが好きだったことに加え、溶接の面白さと奥深さに魅了されたことが決定打となり、同級生の9割が進学する中で溶接事業所への就職を選択。溶接研修で講師を務めた宮本喜行氏が瀧下氏の技量と熱意を買っていて、瀧下氏も宮本氏が勤務する前川製作所の事業内容に興味を持ち就職先として希望した結果、入社に至った。
現在、同社守谷工場のユニットプロダクツ部門製造Gに所属し、主に産業用冷凍機の配管部品の仮付け工程を担当。協働ロボットのオペレーターとして仮付け作業の自動化推進に取り組む。配管部品の形状、サイズは多種多様で、それぞれに適したジグが必要なため、「高校時代に趣味で始めた3Dプリンティングの経験を生かし、職場に導入された3Dプリンターで積層造形のジグを自作している」。目下、積層造形の技術や知識を高めるべく、AM技術者2級の取得を目指し7月の評価試験を受験する予定だ。
将来の夢については少子高齢化に伴う人材不足の深刻化を踏まえ、「AIにより一流溶接士の職人技を再現でき、イレギュラーな事態が生じても臨機応変に対応できる溶接ロボットシステムの開発」を挙げた。実現に向けては膨大なデータの蓄積が課題となることはもちろん、自身が溶接の知見を深めることも必要とし、今後も技量に磨きをかけていきたいとしている。
(「溶接ニュース」2025年6月10日付 1面より)




 SNSシェア
SNSシェア