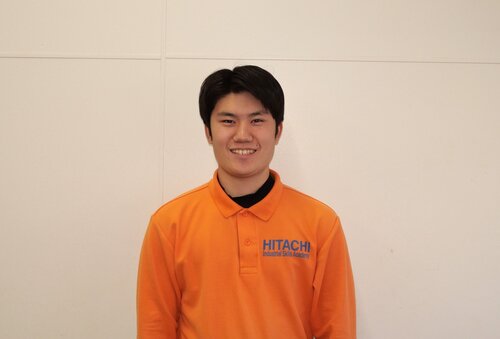溶接を指導した恩師の元に就職 仲間との研鑽が自信はぐくむ(高校生溶接士の将来像)
(「溶接ニュース」2025年6月3日付 1面より)
各都道府県で開催されている高校生を対象とした溶接技術競技会。その名の通り、溶接を学んだ各地の高校生が己の腕を競う競技会であり、溶接技能に青春を捧げた高校生は、その後、どのようなキャリアを積んでいるのかについても注目されている。そこで2014年に長野県高校生溶接技術競技会で優勝し、今も溶接士として活躍する小林広大氏の今を訪ねた。
長野県の溶接産業における重要なイベントの一つが、長野県高校生溶接競技会だ。特に長野県で注目されるのは、長野県を代表する溶接事業所である羽生田鉄工所と前田鉄工所が、それぞれの近隣にある工業高校で溶接技術を指導しているため、教え子同士が競技会で溶接技能を競うこともある。
そんな中、15年に長野県の高校生溶接士の頂点に立ったのが中野立志館高校(長野県中野市)に当時在学していた小林広大氏だ。小林氏は長野県大会を制し、県代表として出場した第6回の関東甲信越高校生溶接コンクールでも優勝を収めた。
当時、小林氏は「羽生田鉄工所の溶接士である安藤誠氏が指導にあたってくださったため、卒業後は羽生田鉄工所で溶接の腕を振るいたい」とコメントしており、その言葉の通り、卒業後は羽生田鉄工所に入社。19年には同社の溶接士として、プロの競技会である長野県溶接技術競技会に出場し、最優秀選手にも選ばれている。
 (小林氏(左)と在学中に溶接を指導した安藤氏)
(小林氏(左)と在学中に溶接を指導した安藤氏)
同社は、1884年に鍛冶屋として創業してから100年以上、長野県で事業を営んできた。圧力容器の製造・販売を事業の柱としており、各種鋼板から産業機械まで、一貫した自社製造による小回りを強みとして、きのこ培地殺菌装置、オートクレーブ、各種処理装置等の受注製造など活躍の幅を広げており、溶接技術を競争力としている。
同社が手がける構造物は3メートルを超える大型構造物も多く、安定した下向溶接だけでなく、不安定な足場でも精度の高い溶接が求められる。そんな高難度な溶接作業に従事する小林氏は、「学生の頃に学んだ溶接技術の基礎は今も自分を支えている」と話す。
工業高校在学中に溶接を学んだ学生でも、進路として、進学や他業種を選択する人が数多くいる中、現在も溶接士としてキャリアを積み重ねていることについて小林氏は「溶接はやればやるほど面白みがわかっていく。高校生のうちに溶接に触れる時間が増えれば、卒業後の進路に溶接士を選ぶ人も増えるのではないか」と話す。
また、「就職後に『技能五輪』の選手として大会に参加する機会をいただいた。その時に、毎日のように溶接技能と向き合い続けた時間が生まれ、溶接技術を格段に向上させてくれた。多くの時間を溶接に費やすことで、溶接士としての自信が芽生えた」(小林氏)。
溶接士として活躍し続けることができていることについて小林氏は、「高校に溶接指導に来たのは当社の先輩社員。その後、入社してきたのが、高校の後輩で、接点やつながりが多く、まるで高校の延長線にいるように和やかな環境だ。多くの仲間のおかげで続いている」という。
仲間やライバルがいる環境でなくとも溶接技術を研鑽することは可能だが、継続して第一線で活躍し続けるためには、仲間やライバルの存在は大きいものだと感じさせる。
(「溶接ニュース」2025年6月3日付 1面より)




 SNSシェア
SNSシェア