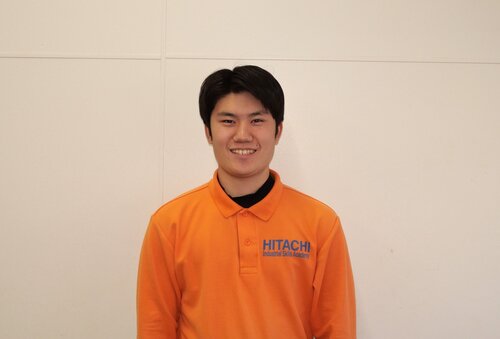将来見据え、若手人材の教育・育成がカギ (未来の溶接士たち)
(「溶接ニュース」2025年1月14日付 14面より)
1990-2000年のいわゆる「失われた10年」の間に、長引く構造不況を背景としてものづくり企業による生産拠点を中国やアジア各地に移転させる動きが活発化し、国内では組み立て、溶接工程をはじめ製造の空洞化が進んだ。これに伴い企業における溶接部門の人員削減、溶接技術者・技能者に対する需要縮小を招き、ひいては溶接教育の需要が減退していった。
かつて企業が海外に生産拠点を置きたがった理由の一つに現地の安価な人件費が挙げられる。その後、2000年代に入って中国の急激な経済成長やアジア諸国における物価や賃金の上昇とともに生産コスト面で国内外の格差が縮まり、加えて日本型デフレによる物価や賃金の停滞、円安が重なったことで日本企業にとって海外展開のうまみがなくなった結果、製造業は国内回帰へと方向を転じることとなった。国内に回帰する企業が増えるにつれ、日本の少子高齢化と相まって人材不足が深刻の度を増し、特に溶接士の不足感が強く、人材の取り合いといった様相を呈している。
失われた10年以降、製造、溶接の空洞化により溶接に関わる教育・研究機関や研究者が減少し、最も多い時と比べて半減してしまった。このため、溶製造の国内回帰が進んで溶接技術者・技能者に対するニーズが戻ってきたとはいえ、肝心の人材が育っていない、あるいは人材の育成に必要な十分な教育機会を提供することが困難な状況に陥っているという。溶接事業所を抱えるものづくり企業の深刻な人材不足を解消する上で、こうした課題への対応が急がれる。
現状、溶接現場の人材不足から、高齢化によるベテラン溶接士の離職や溶接技術習得の難しさなどもあって熟練技術・技能の伝承が途絶え、それらが失われることさえ憂慮される。企業の持続的な成長を維持するためには、技術・技能を継承する若年層の就業希望者を一人でも多く取り込み、人材(人財)へと育成することが重要だ。
(高校生溶接コンクールで協議課題に挑む選手)
そこで、溶接関連企業の採用担当者が溶接士の成り手として期待を寄せる高校生に着目すると、指定機関が工業高校を中心に生徒や教諭を対象とした熟練技能者による溶接指導を支援するなどの教育研修活動が各地でみられるなど、若年層の溶接技能向上を図ろうとする機運の高まりを感じ取れる。また、「全国選抜高校生溶接技術競技会in新居浜」(溶接甲子園)、「高校生ものづくりコンテスト全国大会 溶接部門」といった高校生の溶接日本一を決めるコンクールや、それらへの出場資格をかけて行われる各地区予選大会の存在も大きい。参加選手は腕前を披露することで企業の目に留まり、就職への道が開けることもあり、企業にとっては貴重な人材発掘の場となるだけに注目しており、主催側も運営に熱が入っている様子がうかがえる。
(「溶接ニュース」2025年1月14日付 14面より)




 SNSシェア
SNSシェア