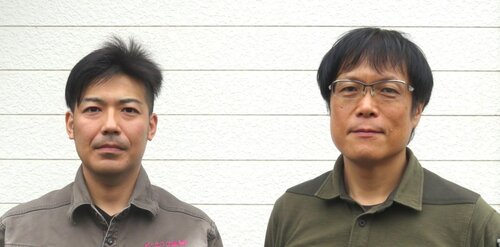第35回新潟県溶接技術競技会「31人の溶接士が腕競う」 12人の注目選手インタビュー
新潟県内で活躍する溶接技能者31人が4月5日、ポリテクセンター新潟(新潟市)に集まった。
新潟県溶接技術競技会は、被覆アーク溶接の部(手溶接)・半自動溶接の部(半自動)・ステンレス溶接の部(ティグ)の3部門で技能を競うもの。
明和工業(株)
・山本選手(ティグ)
「2週間前から1日1時間程度練習してきた。練習時間が満足に取れなかったので、競技会では、とにかくミスをしないように、気を付けて臨みたい。最適な溶接条件を見つけられなかったため、最下位にならないのが目標だ。溶接は、構造物でありながらも、機械と違って、人ぞれぞれ仕上がりが異なるのが面白みだ」・長井選手(手溶接)
「1ヵ月1日5時間練習した。競技会では内部欠陥を出さないことを目標としており、それには、電気を上げて、しっかりと溶融させることが大切だ。目標は3位入賞。溶接はパッと見て個々の実力が把握できるのが面白い。また、上には上がいるのも魅力だと感じる」
TBグローバルテクノロジーズ(株)
・大橋選手(手溶接)
「前回ティグで出場しており、今回は手溶接に挑戦する。ティグと違い大電流で作業を行う手溶接は、思った通りにいかないことが多く、練習時には、難しさに苦難した。初めてのことに挑戦するのは何であっても面白い。ベストを尽くす」・渡邉選手(半自動)
「前回大会も半自動で出場しており、優勝者とは薄板の溶接外観で差がついた。そこで今回は、出場に向けて優勝者の溶接外観の画像を参考に、ビード幅・肉盛高さを調整。できることをやってきたため、自信はあり、当然、目標は優勝だ。溶接競技会はスポーツ同様、勝敗がつくのが面白い」
(株)星野製作所
・横山選手(手溶接)
「半自動の部で優勝した経験があるが、手溶接は初めての参加となる。電流の調整や溶接棒の角度など、調整してきたが、満足な溶接条件を見つけられなかった。自信はないが、ベストを尽くす。溶接の魅力は、手掛けた構造物が形になっていき視認できる点だ」
左から高橋和輝選手、今井雄輝選手
伊藤神也選手、大島啓斗選手
相田一葵選手、大滝未空選手
内田祥平選手(株)総合車両製作所
・高橋選手(ティグ)
「ティグ溶接は外観が特に重要とされる技能のため、ビード幅を揃えられるように練習した。他の部門と違って、曲げ試験は突破する難易度が高くないため、外観で差を出したい。溶接の魅力は技術職であることで、手に職と呼ぶにはピッタリだと思っている」・今井選手(半自動)
「練習の序盤は金属の溶込み量を調整し、終盤で外観を整える練習を積んだ。自信はあるが、曲げ試験を突破できるのかは蓋を開けてみないとわからない。溶接は目で見て上達を実感できるのが面白い」・伊藤選手(半自動)
「初参加だ。他社選手、総合車両の先輩社員と比べて溶接と向き合った時間が少ないため、まずは練習量をこなした。2カ月間、1日10枚程度の練習を繰り返した時間が無駄にならないように、経験にしていきたい。溶接は手作業で職人技と呼ぶに相応しいため、やりがいがある」・大島選手(半自動)
「繋ぎ部分の裏波が出せるのかが、練習中、最も苦慮したポイントだ。各ポイントごとに電気を合わせること、しっかりと、次の層で溶接したポイントに被せていくことに気を付けて本番に臨みたい。肉盛りの高さ、溶接波形など、上達が目で見えるのが溶接の魅力だ」・相田選手(手溶接)
「金属をしっかり溶融させること、外観を整えることの2点を重点的に練習してきた。今回の大会が終わると、競技課題が変更になると聞いているため、過去数回、競技会に向けて積み上げてきた時間を全て出し切りたい。溶接の魅力は、習熟するまで時間がかかることだ。時間がかかるからこそ、上達を実感すると喜びも大きい」・大滝選手(ティグ)
「初めてティグの部に出場する。溶接を始める点・終える点が、ビードが乱れやすいので、本番には注意して臨む。ティグ溶接は特に、溶接ビードの波形がでやすく、成功した時の作品は美しい。仕上がりを見て、外観が整ってると、楽しいと思う」・内田選手(手溶接)
「過去数回、競技会に出場して、溶接条件を変えながら挑んできた。徐々に作る作品のレベルが上がってきていることを実感しているため、ベストを尽くしたい。全国大会に出場した先輩社員などにも相談し、自分だけの溶接条件が整ったため、自信はある。溶接は目で見て成長を実感できるのが魅力だ」
(株)新潟容器製作所
・石川選手(半自動)
「邪魔板の繋ぎ部分と、溶接外観を重点的に練習してきた。優勝は目指しているが、昨年度の自分の作品よりも高い得点を取ることが目標だ。溶接の魅力が奥が深いところだ。触れれば触れた分、新しい課題が見つかって技術研鑽を追求していくと終わりがなく、それが面白い」







 SNSシェア
SNSシェア