先端力学シミュレーション研究所 溶接ひずみ解析普及の歴史振り返る 阪大との二人三脚で築いた独自市場
先端力学シミュレーション研究所(以下:ASTOM)は、プレス成形、溶接、組付け、樹脂成形などの生産技術CAEを得意とするソフトウェアメーカーだ。そんなASTOMの主力商品の一つである溶接ひずみ解析シミュレーションソフトウェア「ASU/WELD-Master(以下:ASU/WELD-Master)」は、大阪大学接合科学研究所・村川英一名誉教授の研究成果を実用化したものである。現在、自動車メーカーを中心に多くの顧客を獲得している。
「溶接ひずみの解析であれば、どこにも負けない」と話す同社の安藤知明元社長(ASTOM元社長)の自信は、溶接研究で世界を牽引してきた大阪大学接合科学研究所とともに、トライ&エラーを20年以上繰り返してきた年月に裏打ちされている。今回のウェルディングメイトでは、ASTOMメンバー(安藤元社長、解析担当後藤、営業担当近藤)と、日本の溶接ひずみ解析の第一人者である阪大の村川名誉教授に、ASU/WELDの開発秘話と今後の展望を聞いた。以後、発言者は敬称を省略して、村川名誉教授、ASTOM側は、安藤元社長、解析担当後藤、営業担当近藤と表記する。
左から安藤元社長、村川名誉教授
ASTOMは、ASU/WELD-Masterを自動車メーカー中心に数多く導入してきた実績を持つ。しかし当然ながら、創業当初から溶接ひずみを解析するソフトウェアの需要が国内外で高まっていたわけではなく、市場が整うまでには多くの時間を要した。
そこには安藤元社長の強い思いと、阪大・村川名誉教授との二人三脚による開発と展開が欠かせなかったという。
阪大接合研究の玄関前に展示されている溶接モニュメント。
1970年大阪万博お祭り広場の大屋根ユニットとして製造され、その後阪大に寄贈された
ASTOMと阪大の結びつきが特に強固になったのは2005年のこと。安藤元社長は、自動車メーカーが課題としていた溶接ひずみ解析について、阪大の村川名誉教授らの研究チームに相談を持ち込んだ。
当時、ASTOMでは同様に村川名誉教授の技術協力のもと、独自に開発した固有ひずみ法を用いた溶接変形解析ソフトウェア「ASU/WELD-Express」を販売していた。しかし、試験ケースでは高精度な結果が得られても、現場では前工程などによって数ミリのずれが生じる構造物も多く、満足な精度を得られないケースがあった。特にアルミ材のスポット溶接ひずみを解析するのは難題だったという。
そこで安藤元社長は、村川名誉教授らが進めていた熱弾塑性解析技術に着目。阪大から特許許諾を受けて、アドバイスを受けながらトライ&エラーを繰り返し、2010年頃、現場での実用化を見据えた「ASU/WELD-Master」を開発した。同ソフトウェアは現場にも対応可能な高精度解析を実現し、販売体制が整った。
しかし課題がなくなったわけではない。解析性能は向上したものの、当時は1メートルサイズの構造物を解析するのに2~3週間の計算時間を要していた。安藤元社長は「当時、ソフトウェア開発に積極的に協力してくださっていた大手自動車メーカーから『解析にかける時間は最長でも1週間』と言われ、本格導入が見送られた」と振り返る。
村川名誉教授
その後、ASTOMの研究開発はNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の国家プロジェクトに採択され、村川名誉教授の助言を得ながら多様な解析法の試作と検証を繰り返した。その結果、村川名誉教授をはじめ深い知見を持つ技術者らによるチューニングで、解析速度は当初の3倍以上に向上。ついに自動車メーカーの生産速度にも対応できるようになった。
結果として、2014年にはトヨタ自動車が発行する技術誌『テクニカルレビュー』にも紹介され、ASTOMの解析シミュレーション技術は世界的な注目を集めた。また、村川名誉教授からは、「ASTOMから相談を受け、自動車分野での溶接の具体的課題やニーズを知り、それにより溶接きれつ進展解析など新しい研究が始まった。産学連携の良い例である」との発言もあった。
安藤元社長は「解析精度は飛躍的に向上したが、その頃からライバルは国内だけでなくなった」と語る。というのも、ASTOMが先行していたとはいえ、海外でも溶接ひずみシミュレーションソフトウェアの研究開発が爆発的に進み始めたからだ。
世界的な大手企業がソフトウェアで市場を席巻していく中、2010年代のASTOMは、小規模ベンチャーとして生き残るため「サポート体制」の強化に力を注いだ。サポート体制とは「顧客の本当の課題に手が届いているか」を検証し続けることだ。安藤元社長は「ソフトウェア市場は右肩上がりに拡大していたが、海外企業のソフトウェアを導入するだけで、短期間に『溶接ひずみの解析』を実現できるとは思えなかった」と話す。
溶接の知見を身につけるには、熟練溶接士でも一般に5年を要する。ましてや「溶接ひずみ解析」となると、当時、正確に理解できる技術者は国内で10人にも満たなかった。つまり、ソフトウェアがあっても、それを実際に運用・検証できる人材が極めて限られていたのだ。村川名誉教授からも、「溶接解析は非常に難しくて、まともにやったら解けないような問題でも、工夫して何とか答えを出すことが、役立つためには絶対必要だ」との話もあった。
「現在普及しているソフトウェアの多くは、CADデータで工程を管理するものが主流で、重複作業の削減などは可能だが、前工程の変形や応力を見込むなどの暗黙知を含む技術や技能をデータ化する段階には至っていない」と安藤元社長は語る。また、解析担当後藤は「当時、幅広い工程に手を広げず、溶接ひずみという特殊な領域に特化して開発を続けた結果、当社では約400件を超える解析実績を積み上げた。これは国内では間違いなくナンバーワン、世界でも稀有な経験値だ」と胸を張る。
安藤元社長
多くの解析を国内で手がけてきたASTOMだが、課題の一つは、自動車メーカーなど大企業との協業が多いため、同社の判断だけで実績を公表できない点にある。また、解析速度は飛躍的に向上したものの、5メートルを超える大型構造物への対応は今後の課題だという。
営業担当近藤は「ホームページや口コミで『自社製品を解析してほしい』という依頼は増えているが、ソフトウェアそのものの販売件数はまだこれから。当社のソフトウェアは、ホームページを見て即決購入できるような性質の製品ではない」と語る。
現在も課題は残るが、コロナ禍以降、溶接ひずみ解析ソフトウェア市場には変化が生まれている。特に2024国際ウエルディングショーでは「当社に相談を寄せるのが一般従業員ではなく管理職になった」と感じたという。
これは、量産ラインの自動化や効率化が一巡し、ソフトウェアの導入に関心を持つ企業が増えたことを示している。また、円安や海外ソフトウェアベンダーの値上げによって、海外製ソフトウェアの更新を見直す企業が増えたことも背景にある。
営業担当近藤は「海外企業は幅広い品揃えでソフトウェアサービスを展開しているが、"品揃え"だけで満足できない質を求める企業を満足させられるのは当社だけだと自負している。試していただければ、少しずつ口コミで広がるはず」と話す。







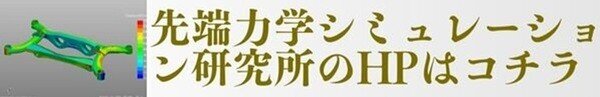
 SNSシェア
SNSシェア



